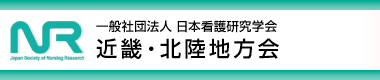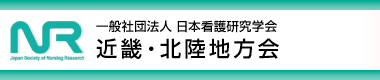皆様、新型コロナウイルス感染拡大で不安と緊張の日々をお過しのことと存じます。
この度、初めてリレーブログに記事を投稿することになりました滋賀県立大学人間看護学部基礎看護学講座の米田照美です。私は看護師・看護学生を対象に療養環境や援助場面の観察時における視線を計測し、危険認知の特徴を明らかにする研究を行っています。また、それと並行して看護学生を対象とした体験学習型の医療安全教育にも取り組んでいます。今回は本学(本学部)で取り組んできた医療安全教育についてご紹介いたします。
看護学生が臨地実習で経験するヒヤリハット(インシデント)は一部の研究報告によると4割〜7割と言われています。本学部でも一度、調査しましたが、在学中に約4割の学生がヒヤリハットを体験していることが分かりました。学生に対して医療事故の危険性については、たびたび授業や実習で説明・指導してきましたがなかなか実感を持って理解してもらうことが難しいと感じていました。看護技術の練習では学生同士で患者役・看護者役を行うことが多く、緊張感がなく、看護者役が説明する前に患者役が先に動いてしまう場面も多く見受けられました。
ある日の朝、NHK「おはよう日本」のニュース番組で高校生や中学生を対象とした交通安全教室で実際に生身の身体で車にはねられる場面を再現しているスタントマンを観ました。この時、ふと、ひらめきこの方々に医療事故の転倒や転落事故の場面を演じてもらえれば医療事故の危険性をリアルに伝えることができるのではないかと考えました。すぐに警察署に問い合わせて事情を説明したところ、スタントマン専属事務所の倉田プロモーションさんを紹介して下さいました。事務所の方も初めての依頼ということで何度が打ち合わせを重ねながら授業計画を練り上げ、患者役をスタントマンが演じる医療安全教育を実現することができました。
演習では医療事故の危険性をいかにリアルに伝えるかということに重点を置きました。医療事故の再現劇では、スタントマンの方に骨折や麻痺などの障がいのある患者役や高齢で歩行移動が難しい患者役を演じてもらい、移動や移乗介助時の転倒や転落シーンを実際に生身の身体で演じてもらいました。さらに、学生にはスタントマンの演じる片麻痺のある高齢患者さんの車いす移乗援助を実践してもらいました。車いす移乗の実践では学生の援助技術が悪いとスタントマンさんが容赦なく転倒・転落・滑落して頂けるので、見ている側も実践する側もいつもより緊張感を持って臨床に近い状況で取り組めました。演習後の学生の感想では、普段練習している学生の患者役との違いにかなり戸惑い、その中で患者を安全に援助することの難しさを実感したと記述する学生が多かったです。また、体験を振り返り、自己の看護技術の未熟さ、知識不足、患者への説明不足、観察不足、注意不足が原因となり、医療事故が容易に起こることを理解したという記述も多くみられました。この演習後、多くの学生は医療事故を他人事ではなく自分自身の問題として捉え、演習前と比べて医療安全への意識が向上したのではないかと手ごたえを感じています。
令和2年度はコロナ禍のため対面授業が中止となり、この演習も実施できませんでした。今年度もどうなるかわかりませんが、感染拡大の中、病院実習や学内演習の実施も厳しく、今後はオンライン学習でもよりリアルに学習できる医療安全教育の開発が必要になってくるのではないかと思っています。一日も早くコロナ感染が収束し、日常の看護教育に戻れることを祈るばかりです。
【研究者URL】
研究紹介|滋賀県立大学人間看護学部 基礎看護領域 (usp.ac.jp)
http://www.nurse.usp.ac.jp/kiso/research_04.html