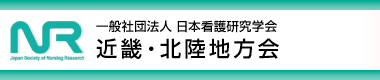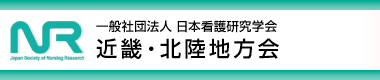みなさま、こんにちは。
和歌山県立医科大学保健看護学部の水田真由美です。
今年の8月の学術集会の紹介をさせていただきます。
本学の学科長 岩村龍子が大会長を務めます第12回和歌山保健看護学会術集会のご案内です。
和歌山保健看護学会は、2009年に和歌山県立医科大学保健看護学会として設立され、2018年に和歌山保健看護学会と名称を変更しました。保健看護学の進歩発展と会員相互の研鑽・親睦を図り、保健・医療の向上に資することを目的としております。和歌山県外からのご参加もお待ちしております。
今回は「看護専門職としての発展に向けたキャリア形成」をテーマに、みなさまと活発に交流し、元気が出るような会にしていきたいと思っております。
特別講演には、兵庫県立大学の増野園惠先生をお招きして、「元気が出るキャリア論」をお話して頂く予定です。また、研究発表の一般演題を募集いたしますので、日頃の実践や研究の意見交換をして頂ければ幸いです。演題募集は、5月を予定しております。詳細は下記のホームページに掲載予定です。現在はまだ、アップしておりませんが、昨年の要領はご覧になれます。
みなさまのご参加をお待ちしております。
日時:2020年8月30日(日)
場所:和歌山県立医科大学保健看護学部
【ホームページ】
https://www.wakayama-med.ac.jp/usermenu/alumni/hokenkango-gakkai/index.html