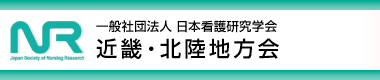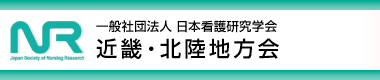|
四天王寺大学大学院 泊 祐子さん
この3月に第38回地方会(於:京都キャンパスプラザ)に久しぶりにじっくりと関わり、大変懐かしく感じました。なぜ、そんなに懐かしいのか。皆様にお話しさせていただきたいと思います。
<特看卒業生としての本学会への思い出>
本学会、発足当初は四大学看護学研究会の名称でした。4つの国立(弘前・千葉・徳島・熊本)大学の教育学部特別教科(看護)教員養成課程の教員の勉強会から発足したものです。四大学の先生方が看護を議論する学会がない状況に対して、看護学の発展を望まれて、日本で初めての看護の学会を設立されました。学会名に四大学という冠では、閉鎖的な印象を与え、入会をしにくくするのではないかという意図から、1981年に現在の名称に変更しています。教育学部特別教科(看護)教員養成課程は高等学校の衛生看護学科の教員養成を目的に1966年に熊本大学と弘前大学の設立を皮切りに、徳島大学、千葉大学に設立されましたが、2003年弘前大学が医学部保健学科への改組となり、四大学の「特看」と呼ばれた教育学部特別教科(看護)教員養成課程の幕は閉じました。特看の卒業生である私たちは自分たちのことを絶滅危惧種と感じています。
特看の先生方が設立してくださった本学会は、多くの看護職に学ぶ機会の恩恵をくださいました。実習や卒業研究をした頃の恩師とのやりとりやお顔が思い浮かびます。一クラス20人という贅沢な教育でした。
本学会の第1回学術集会は1975年に徳島大学で開催され、学生だった私は階段教室の上の方から参加していました。何のことが十分にはわかりませんでしたが、こんな風に研究をするのかと感じた覚えがあります。然るに、私の入会は1977年に恩師の故福井公明先生から入会案内のお手紙をいただき、2000円の年会費を送ったことで始まりました。のちに福井先生に2000円を現金封筒で送って来たのは私だけと言われたので、記憶に残っています。その後、千葉や弘前や熊本で開催される学術集会に参加し、恩師と交流させてもらったこと、また、毎回繰り広げられる学術集会のシンポジウムでの激しい議論はとても迫力がありましたが、議論の内容がわからず、後から恩師に解説してもらった覚えがあります。それらは大きな糧となり、研究や看護実践の見かたへの示唆を得ました。青森や熊本で開催される学術集会には、夜行列車に乗ったことが懐かしく思い出されます。
<地方会の発足当初と本学会を通しての学び>
地方会の発足は、地区割がまだC地区という近畿・四国地方会だった頃に、「徳島大学の同窓会をするから」と京都駅隣のセンチュリーホテルのロビーに集合の声がかかった時の1986年でした。そこには、野島良子先生(名誉会員)、近田敬子先生(名誉会員2022年ご逝去)、中木高夫先生(名誉会員)、玄田公子先生、早川和生先生たちがおられて、地方会の発足の相談でした。地方会事務局を玄田先生が担当されることが決まり、第1回は近田敬子先生、2回目は早川和生先生が実行委員長を務められて、京都で開催されました。3回目を秋吉博登先生が担当され徳島での開催でした。集まられた先生方の地方会のモットーは「わいわい、がやがや、楽しい集まりにしよう」でした。若手が演題を発表しやすい場にすることや、また、座長も若手が担い座長の役割を学ぶようにと、当時、若手だった私もさせてもらいました。幾度か座長を経験しながら、会場を楽しく討論できる雰囲気にと、質問の振り方や、質問者の意図を解釈して、演者に返す等の役割を学んでいきました。
第12回(1999年3月)の地方会を担当させていただき、当時勤務していた滋賀医科大学看護学科棟で開催しました。メインテーマを『人々の生活の営みと看護活動』とつけて、日常の中に看護を考えるという意図を示しました。滋賀県ならではの琵琶湖博物館の学芸員の方に琵琶湖の水質とその諸問題の特別講演と、この地方会では初めてとなるワークショップ計画し、「老人のActivity Care」、「日本人の死生観とターミナルケア」と「教育の現場から見た在宅看護活動」のテーマで、それぞれコーディネーターを中心に活発な討論をしてもらいました。気軽な討論ができることで、頭の活性化が図られることを改めて思い出しました。
このような形で地方会の事務局や世話人会に参画させてもらい、多くの先生方との交流を通して学ばせていただきました。既に半世紀近く過ごし、感慨深く思っています。
大学院教育に携わり4分の一世紀になりますが、院生たちとの討論は、思索すること、それぞれが求めているモヤモヤした十分にことばにできない事柄を追求する思考です。説明概念は何か、中心は何?などのゼミの形式は地方会からの学びが多かったかもしれません。
次回は、「日本看護研究学会と共に(2) 研究の徒然」をテーマにしたいと思います。
|