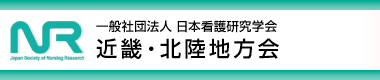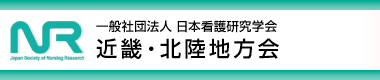数年ぶりの寒波到来で、各地で大雪となっております。
比較的温暖な大阪北摂地域にある本学では、積雪はないものの、隣接する継体天皇陵(太田茶臼山古墳)の堀に氷がはりました。勤続ウン十年のスタッフも、めったに見たことがないそうです。
さて、藍野大学キャリア開発・研究センターでは、定期的に講演会・セミナー・公開講座を開催しております。今年度も多くの方のご参加をいただき、好評のうちに終了しました。
平成29年度 講演会・セミナー・公開講座
6月 セミナー「レポート・論文作成の作法とコツ」
7月 セミナー「管理と倫理のはざまで」
講師:オフィスKATSUHARA 代表 勝原裕美子 先生
8月 循環器看護セミナー1「よくわかる!PCPSとIABP(基礎編)」
環器看護セミナー2「ナースのためのPCPS・IABP(臨床編)」
セミナー「生体情報モニタで知っておきたいポイント」
9月 講演会「わたしがもういちど看護師長をするなら」
講師:日本看護協会会長 坂本すが 先生
10月 セミナー「看護研究の読み書きに必要な統計学の知識---基礎編---」
講師:キャリア開発・研究センター長 / 藍野大学 副学長 菅田 勝也 先生
11月 セミナー「〜喜びがある、大切さを知る〜摂食・嚥下リハビリテーション」
講師:ナーシングホーム気の里 施設長 田中靖代 先生
12月 公開講座「ヘルスケアサービス管理論 」
講師:公益社団法人日本看護協会 副会長 齋藤訓子 先生
公開講座「看護組織管理論 」
講師:福井医療短期大学 教授・PNS研究会 会長 橘幸子 先生(午前の部)
固定チームナーシング研究会 会長 西元勝子 先生(午後の部)
1月 公開講座「ヘルスケアサービス管理論
講師:公益財団法人日本医療機能評価機構 執行理事 橋本廸生 先生
平成30年度第1回セミナーは、5月26日(土)「診療報酬改定について(仮題)」をテーマに、
日本看護協会副会長の齋藤訓子先生を講師にお迎えする予定です。
詳細については、近々ホームページにアップいたします。(http://cdr.aino.ac.jp/#)
皆様のご参加をお待ちしています。